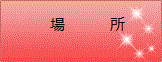身近にある色彩心理

実は、色彩心理学は、まだ学問として確立されていません。
色彩検定などを勉強すると、色の対比、同比などの「知覚心理学」
について学びますが、一般的な認識としては、
例えば、ピンクを好きな人はどんな性格?
赤が気になるときは、どんな気分?のようなことではないでしょうか。
広義で捉えると、色彩心理は、
連想作用、象徴作用、感情効果、共感覚などがあります。
進化の過程で、私たちの祖先は、
色を1つの情報として捉える事で、生き残って来ました。
血や太陽や火などの赤を見る体験を何度も何度もした結果…
赤は、戦いの色、赤はエネルギーの色、赤は情熱の色となりました。
これが人間の根源にある色の意味合いとされています。
また、連想から、色に様々な色名がつけられています。
そこには、時代背景などの歴史やその国独特の文化が関係します。
その為、特定の色に対するイメージは、国や時代によっても異なります。
カラーセラピーは、人間の根源にある色の意味合いの他に
このような文化や歴史的な背景にある色の意味合いなども
色彩言語として用います。
……つづく
2013年06月27日 Posted byリアノン at 18:20 │Comments(0) │セラピー
コメント承認はオーナーが承認